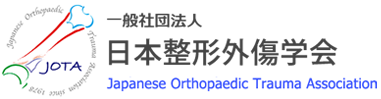一般の方へ
 骨折の解説
骨折の解説
こどもの骨折
こどもの骨折では、大人と異なる特徴・注意点が色々とあります。それらについて解説します。
骨が治るのが早い
こどもの骨は、大人に比べて治る能力(くっつく能力)が高いです(図1,2)。年齢が低いほど早く、赤ちゃんの骨折はあっという間に治ってしまいます。ギプス治療の期間などが短くて済むことは長所ですが、逆に言えば、早く適切な治療を受けないといけないとも言えます。
自家矯正能(骨が元の形に戻る能力)がある
また、こどもの骨折では、大人と違って自家矯正能が見られます(図1,2)。大人では、骨折がずれてくっつくと基本的にはそのままです。一方、こどもでは、骨折が一旦ずれたまま変形して治っても、数年かけて自然に形が元に戻ることが多く見られます。レントゲンで骨がずれているのに、手術ではなくて「ギプスで治しましょう」と言われた場合は、この自家矯正能を見越した選択です。
ただし、年齢・場所・ずれの方向による差が大きく、どの程度自家矯正が期待できるかは、整形外科医による判断が必要です。回旋変形(捻じれている骨折)は許容ができませんが、屈曲伸展変形についてはある程度許容ができます。条件によっては、小さいこどもでも自家矯正がほとんど期待できないことがあり、2mm程度のずれでも手術が必要になることもあります(幼児から小学校低学年くらいまでは骨折の保存治療の許容範囲は広くありますが、小学校中~高学年以降になると骨折の保存加療の許容範囲も狭まります)。
図1. 8歳男児。左鎖骨骨折。
骨は大きくずれていますが、保存治療を行いました。1ヵ月後、骨はずれたままですが、もやもやとした新しい骨が見え、3ヵ月後にしっかりした骨でくっついています。1年半後には自家矯正が見られ、骨折したことがわからないほどに治っています。
A:骨折直後
B:1ヵ月後
C:3ヵ月後
D:1年半後
図2. 0歳女児。左大腿骨骨折。
牽引治療(脚を引っ張る治療)を行いました。骨折から2週間後に、もやもやとした新しい骨が見え、1ヵ月後にしっかりした骨でくっついています。1年後には自家矯正して、骨折したことがわからないようほどに治っています。
A:骨折直後
B:2週間後
C:1ヵ月後
D:1年後
骨折しているかも?
骨折していれば、普通はレントゲンで折れている部分がわかります。しかし、薄いヒビのような骨折、骨の端にある軟骨部分の骨折では、レントゲンでは判断ができないことがあります。これらの場合、「骨折していないとは言えないので、後日もう一度レントゲン撮影しましょう」ということになります。
また、救急病院の休日・夜間診療などは、整形外科医ではない医師によって行われていることがあります。判断が難しい場合は、「翌日に整形外科医による診断を受けてください」という説明がされます。
少しでも正しく、骨折の有無・ずれの程度などを判断するために、同じ部位を色々な方向から撮影したり、健側(逆側)の手足と比べるなどの方法を取りますが、それでもわからないことがあります。数日から数週間経ったことで骨折線がはっきりしたり、新しく骨ができたことでやっと骨折していたことがわかることもあります(図3)。その間は、念のためギプス等で固定をして、ずれを進行させないことが大事です。
図3. 1歳女児。転倒し、右肘が腫れているため整形外科を受診されました。レントゲンで明らかな骨折は指摘されず、おそらく打撲でしょうという判断になりました。1ヵ月後のレントゲンで骨の表面に沿って薄い骨が見え、骨折していたことがはっきりしました。最初のレントゲンを見返しても、はっきりとした骨折はわかりません。
A:受傷直後
B:1ヵ月後
画像検査について
骨折があるかないかの評価には、レントゲンが基本になります。しかし、こどもの骨は軟骨が多く、軟骨はレントゲンに写らないため、骨折があるのかどうか?治療が必要かどうか?の判断に困ることが少なくありません。
そこで、超音波、MRI、CTなどを追加することがあります。超音波とMRIは人体に無害ですが、じっとできない乳幼児には難しいこともあります。CTは被曝を伴うため、こどもに対しては安易に撮影しない方が良いですが、必要なことがあります。
保存治療の適応が広い
骨折の治療法は、保存治療と手術治療に分かれます。保存治療とは、簡単に言えば手術以外の治療法で、ギプスやシーネによる固定、牽引などの治療を指します。 こどもの骨折では、自家矯正能が見られるため、手術で骨の形をまっすぐきれいに治す必要がなく、ある程度ずれていても保存治療を選択することがあります。 一方、最初は保存治療を行っていても、徐々にずれが進めば、後から手術が必要になることもあります(図4)。
図4. 2歳男児。右肘の骨折。受傷直後は上腕骨の下の端に薄くひびが入っていますが、ほとんどずれておらず、ギプス治療となりました。2週間後、大きくずれて、手術が必要になりました。
A:骨折直後
B:2週間後
C:手術後
手術について
こどもの骨折では保存治療の適応が広いですが、もちろん手術が必要なこともあります。ずれが大きい場合、年齢が高い場合、関節(骨と骨のつなぎ目)近くの骨折や、成長軟骨板の骨折では手術になる可能性が上がります。
お子さんに手術が必要と言われると、全身麻酔や身体にメスを入れることについて、ご心配なこともあると思います。麻酔や手術にも合併症はありますが、確率としては非常に低いので心配しすぎず、適切な治療を受けてください。
また、必ずしも手術が必要ではないですが治療期間が短くなる、入院期間が短くなる、松葉杖の期間が短くなる、などのメリットがある場合は、患者さんのご希望・事情に沿って手術治療を選択することもあります。
成長軟骨板について
こどもの骨の両端の成長する部分を成長軟骨板と呼びます。骨の成長はこの部分で起こっているため、成長軟骨板の損傷には注意が必要です。成長軟骨板がダメージを受けると、それ以後の成長が阻害され、反対側と比べて短くなってしまったりします。これは小さいこどもの骨折ほど著明になります。また、骨の一部だけに成長障害が生じると、障害部は伸びられないものの、正常部が伸びるので、徐々に変形が生じてしまいます(図5)。そのため、成長軟骨板の骨折では、治療を慎重にしなければなりません。
図5. 9歳男児。左膝の成長軟骨板の骨折。受傷直後は大腿骨(上側の骨)の外側(写真右側)が縦に折れていますが、ずれは少なく、保存治療となりました。外側(写真右側)の成長が止まったため、内側(写真左側)が伸びることで徐々に骨が変形し、1年半後に強い変形になってしまいました。両脚全体の写真で左膝が強く外に曲がってしまっています。
A:骨折直後
B:1年半後
C:1年半後の両脚全体
過成長と成長障害
こどもの骨折は、治った後に骨の長さが骨折前より長くなることが多く、過成長と言います。そのため、脚の骨折では、骨折側の脚の長さが反対側と比べて長くなり、脚長差(脚の長さの左右差)が生じることがあります。1cm程度の差であればほとんど困りませんが、2cm以上になると長さを合わせるための治療も考えなければいけません(図6)。チェックのために、最低でも数年は通院することが望ましいです。
逆に、成長軟骨板の骨折では、成長が障害されて、逆側と比べて短くなることがあります。
図6. 6歳男児。左大腿骨骨折。手術が行われ、骨はきれいな形に固定されました。徐々に左大腿骨が過成長し、5年後に左右差が2.5cmになり、立って撮影したレントゲンで骨盤が傾いています。脚の長さを合わせるための追加手術が必要になりました。長期的なチェックが必要であることの例です。
A:骨折直後
B:手術後
C:5年後
長期のチェックが必要
大人の骨折では、骨折から数か月が経って、骨がくっついた段階で診察は終了になることも多いです。一方、こどもでは一旦骨がくっついても、その後に、長さや形が変化してくることがあるため、長期間の定期的な診察が望ましいです。骨折が治って何も困っていないのにどうしてまだ診察が必要なのか?と思われるかもしれませんが、そのような理由でチェックが必要なのです。
2024年11月